元亀元年 十月三日 岡山城
「なに? 宗景が小佐々の使者と会っておっただと? いつじゃ?」
宇喜多直家は、決裁書類を読んでいた手を止めて聞く。
「は、一昨日、小豆島の小海城山城(おみじょうやまじょう)にて、会談が開かれたもようです」
重臣の戸川秀安が答えた。
「なに? どのような話なのだ?」
「それが、詳しくはわかりませぬが、周辺の松田氏ら国人にも書状が届き、服属するや否やという内容らしいのです」
「なにい? われら宇喜多にはそのような書状は来ておらぬぞ。秀安よ、何か知っておるか」
「いえ、それがしは何も。われらにそのような書状が来ているとは、聞いておりませぬ」
直家は考え込んだ。これは、まずい。
何か良からぬ事がわれらの知らぬところで動いている、と。小佐々純正が、いったい何のために近隣の大名国人に服属を迫っているのだ?
いや、何のためなど考える余地もない。自らの力を増すためだ。問題は、なぜわれらには使者がこないのか、という事だ。
「殿、断言は出来ませぬが、われらに服属を促す使者が来ていないということは、つまり……その意思がないという事かと」
「……」
秀安の言っている事はもっともだ。
服属させないと言うことは、そのまま残すという事なのだろうか? しかし、それはあり得ない。残す意味がない。そもそもなぜわれらなのだ?
伊賀に原田に竹内に後藤、いくらでも他に国人はいる。なにか恨みを買うような事をしたか? いや、待て、今そのような事を考えても仕方がない。
「秀安よ、まずは情報が欲しい。宗景はもとより、近隣の国人へ忍びを送り込み調べさせよ。どのような些事でもかまわぬ。判断はこちらでするゆえ、すべて知らせよ、と」
「はは」
直家はさらに考えた。逆ならどうだ? 残すのではなく、潰すつもりなら?
むしろそう考える方が合点がいく。われら宇喜多は浦上に従っているとは言え、独立した国人である。
友好関係にある浦上を服属させ、われらを削れば、浦上の力を大きく削ぐことになる。しかしそれだけならば、他の国人を二つ三つ滅ぼしても同じ事だ。
何かある。われらを滅ぼして小佐々が得るものが、何かあるのだ。
「殿、実はもうひとつ」
「なんじゃ、まだあるのか」
「は、こたびの浦上の服属とは関わりがないと思われますが、尼子の残党がしきりに小佐々に接触をしているようにございます」
「尼子だと?」
直家の顔色が変わった。尼子の残党といえば山中幸盛か。
昨年永禄十二年に反毛利で決起し、一時は出雲、伯耆、因幡、備後、備中、美作においておおいに勢力を拡大したものの、毛利軍の反撃をうけ、失敗に終わったのだ。
隠岐に逃れたとは聞いていたが、再起が早いな。
「尼子が小佐々に……目的は一つ、支援であろうな」
「は、それがしもそう考えまする。前回も各方面から支援を受けましたが失敗しました。こたびは西国一の小佐々と結ぶことで、万全を期すつもりなのでしょう」
おそらく小佐々は単独で毛利と戦っても勝てるだろう。
しかし毛利も、まがりなりにも長門から備中、伯耆まで八ヶ国を統べる太守だ。戦えば小佐々も無傷ではすまない。
「しかし毛利と小佐々は不可侵条約を結んでおる。尼子を助けるとなると、毛利を敵に回すことになるが、純正はやるだろうか」
「わかりませぬ。しかし、妙な噂を聞き申した」
「どんな噂じゃ」
「はい、昨年の小佐々の伊予攻めの件なのですが、明らかに小佐々が優勢なのにも関わらず、平定に半年以上もかかりました」
「ふむ。伊予一国ならまだしも、南の宇和郡の平定のみ、刻がかかっておる」
「はい。実は、伊予の宇都宮が密かに毛利と通じ、兵糧矢弾を西園寺に流していたというのです」
「なに? ! それが真なら、毛利は直接ではないにしろ、小佐々との盟約に反する行いをしているではないか」
直家は驚きを隠せない。
「はい、そうなります。それが露見したかはわかりませぬが、伊予平定後に宇都宮は改易され、喜多郡には別の者が入っております」
「そうなると、毛利と小佐々は表向き手を結んではおるが、その実、戦の火種がくすぶっているとも考えられるな」
直家の顔が、悪代官のような陰謀を考えている時の顔になる。
「秀安よ、他になにか変わったことはないか? このような時は、何でもないように思える事こそ、問題解決の鍵を握っている場合があるのだ。ないか?」
「関係があるかわかりませぬが……」
「よい、申せ」
「は、われらの当面の敵は毛利、つまるところ隣国の三村でございましたが、それゆえ気にもとめておりませなんだ」
「なんだ?」
「はい、実は三村と小佐々も近ごろは商人が頻繁に往来し、人も動いているようにございます」
普段なら気にもとめないような事だが、直家は妙に引っかかった。
「……毛利と小佐々は、言ってしまえば冷え切っている。にもかかわらず、三村と近づいている、だと?」
なぜだ? 直家は疑問に思った。毛利の影響下にある三村と、単独で毛利以上に親密になるなど、何を考えているのだ?
「小佐々が三村と誼を結ぶ、なにがある? 毛利と親交を結ぶ、結ばない、敵対する。敵対するとすれば、敵の力を弱める……」
毛利と小佐々が不可侵を結んではや三年となる。
まだ小佐々が、島津はおろか大友も降していない頃だ。よくよく考えると、異常なほどの早さの領土の拡がりだ。
いったい小佐々純正という人間は何者なのだ?
考えれば考えるほど、直家の頭は混乱する。そしてその三年の間、攻守の盟にはせず、毛利とは不可侵のままだ。
それすなわち、当時から毛利の援軍はなくとも、攻められさえしなければ、単独で大友と当たれると考えていたからだ。事実そうなった。
着実に筑前、筑後、北肥後を押さえ、大友を弱体化させつつ自らの力を強めていった。
「毛利を弱体化させる……自分の力を強める……三村か!」
三村を寝返らせる事ができれば、そのまま備中を手に入れる事になり、毛利にとっては看過できない一大事である。
「しかし三村がそう簡単に寝返るだろうか? 三村とわれらは不倶戴天の敵、われらが浦上を頼みとすれば、三村は毛利を頼みとしておる。この構図は簡単には崩れぬ」。
秀安は直家の思考の邪魔をしないよう、傍らで静かに聞いている。
「まて、最初に戻ろう。小佐々がわれらを潰すつもりで、浦上やそのほかの国人を服属させるとしよう。われらとしてはどうすべきか? 秀安、どう思う? もしそうならわれらはどうすべきだ?」
「は、まずは家を保つために、自ら小佐々に服属を願い出るのが一つ、そしてもう一つは織田に使者を出し、小佐々との仲を取り持って貰うこと。そして最後は毛利にござる」。
直家は、秀安が言う三つの方法を考えてみる。
「小佐々に服属を願いでて、かなうと思うか? もしかなうなら、なぜわれらには使者が来ぬのだ。道理があわぬ」。
秀安はうなずく。
「では次に信長だ。われらは以前信長に敵対しておる。そして今、信長は一揆攻めの最中であろう? われらに関わっている暇はないのではないか?」
確かにその通りだ。それに畿内となれば時間もかかる。
「残るは毛利だが、服属できるだろうか」
「何事もなければ、敵だったものが服属を申し出てくるのです。断る理由はありませぬ。しかし……」
「しかし、なんだ? ……あ!」
「そうです。三村です。不倶戴天のわれらと手を結ぶなど、元親が許すはずもありませぬ。間違いなく反発します」。
「そうなると、反発した三村は誰を頼りにするか……つながった! 純正を頼る! そうなれば毛利はかなりの痛手だ。しかし、これはまずいな」
直家は眉間にしわを寄せ、考え込む。万事休すなのか。
「わしが輝元なら、間違いなくわれらではなく三村をとる。備前の十四万石と、備中の三十六万石なら考えるまでもない」
「さようにございます。浦上が純正に服属するなど関係なく、三村に合力して孤立したわれらを攻めれば良い話です」
「くそう! これでは八方塞がりではないか。どうする事もできぬ。座して死を待つより他はないのか。なにか、ないか」
直家はイライラが募っている。謀将直家も、もはや策がないのであろうか。
「殿、一つだけ、策がないこともございませぬ」
なに? と直家は秀安の言葉に目を輝かせた。

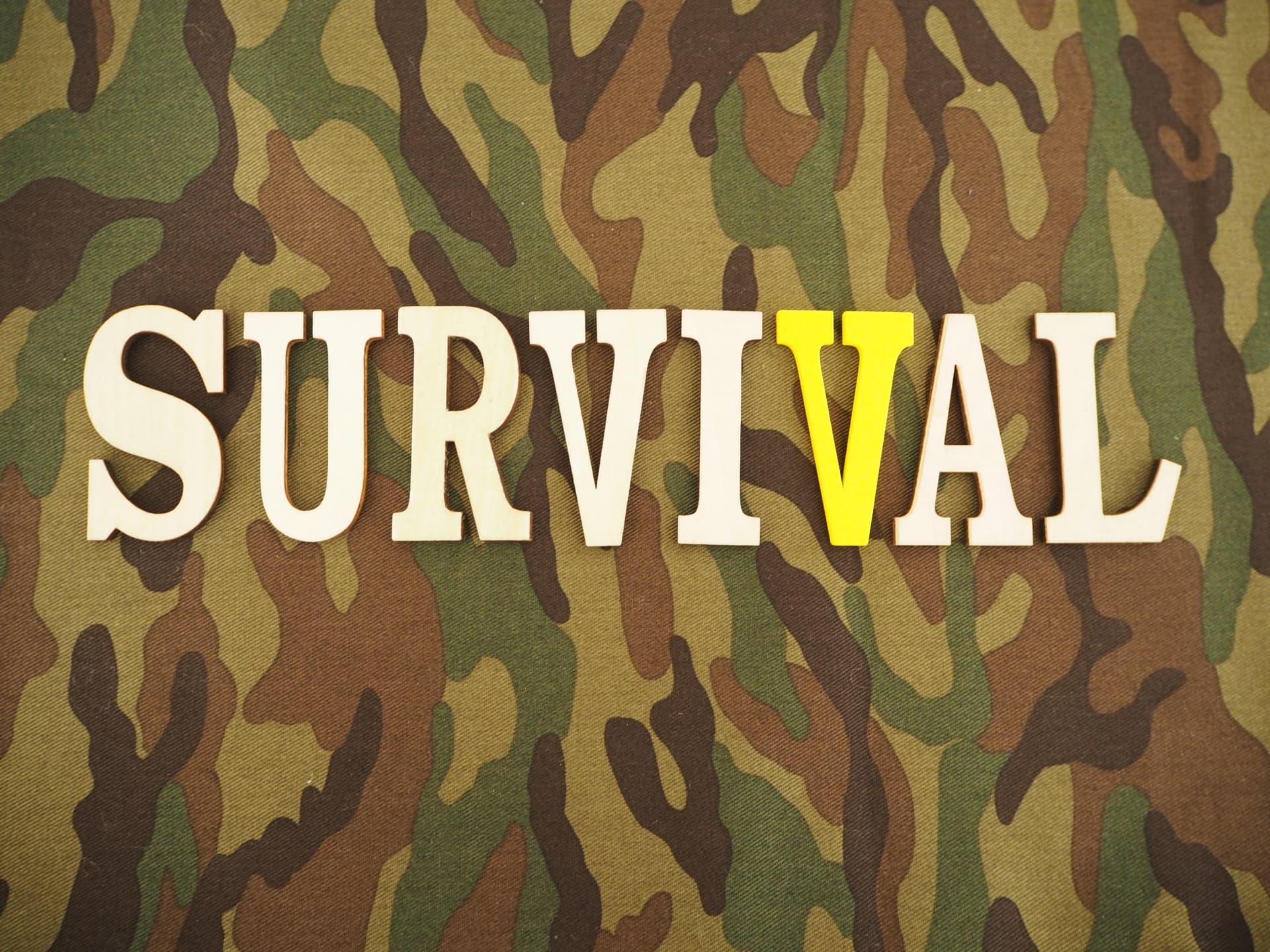


コメント