永禄十二年 十月二十三日 三河 岡崎城
「忠次よ、小佐々との件どうなっておる」
「は、弾正忠(織田)様のお許しも得たゆえ、正式に小佐々家との通商を開始する運びとなりました。ただいま商人を通じた取引の協議が行われております」
うむ、と家康はうなずいた。
東の武田が脅威である。協定を破って遠江へ侵攻してきているからだ。武田とは手切れとなり、交戦状態が続いている。織田と徳川の盟約はあれど、心もとない。
今は少しでも味方が必要なのだ。
「交易はもちろんだが、鉄砲や矢弾よの。いくらあっても多すぎる事はない」。
ああそうだ! と家康は思い出したように口に出した。
「弾正忠殿は、小佐々家に留学生なるものを送っているというではないか。わが家中も見習って送りたいが、どうだ」
「よきお考えです。新しいものを学び、役立て、次代につなげる。さっそく人選に入ります」。
石川数正が答えると、家康はうむ、と返事をして上機嫌になった。
■南近江 三雲城
「殿、小佐々からの文にあった事、どのようにされるのですか」
「わしはもう殿ではない。予想通りの返答よ。佐々木一門としてお助けしたいのはやまやまであるが、六角は盟約を結んでいる織田の敵ゆえ、盟を結ぶことあたわず、交易もしかり、当然よな」
父である三雲行定と同様に、六角定頼より家中を支えてきた重臣である三雲定持からの問いに、承禎はそう答えるしかなかった。
「定持よ、わしの世代とせがれの世代は、父の代のようにはいかなんだ。今織田は北伊勢のみならず南伊勢も押さえ、われらは四方を囲まれておる。伊賀にも味方はおるが、いつ裏切るかわからぬ」
承禎は悲痛な面持ちである。
「まずは織田との和議をなせ、と言うてきおった。もし、お気持ちがお有りなら仲立ちをする、とも。誰が上でもない、朝廷や幕府に従うと思えばよい、とな」
定持は黙って聞いている。
「家門の誉れや権威や秩序、わしはそれこそが大事と考えておった。現にそれに従ってこの地を治めてまいった。皆もそれに従った。しかし、圧倒的な力の前には、権威など、役にたたぬ。そう悟ったのだ」。
承禎はなおも続ける。
「わしは織田に和議を申し込もうと思う。もはや織田を倒し父の代の栄光を取り戻すことあたわぬ。定持よ、国人や家臣の説得を頼めるか? 今は義定が当主ゆえ、あやつも説得せねばならぬが、義治と義定はわしが話をしよう」
「よくぞ、ご決断なさいました。この定持、身命を賭して任にあたりまする」
うむ、と承禎は答え、小佐々へ仲介依頼の書状を書くことにした。
二人の息子と家臣や国人衆の反対が考えられるなか、六角氏は、路線を反織田から親織田へ変更をしたのであった。
■北近江 小谷城
「殿、弾正忠様との街道整備の件、滞りなく話が進んでおりまする。小佐々との折衝も問題なく、大使館を通じて堺の商人とのつても広がっております」
そう話すのは宮部継潤である。
浅井長政は同盟相手の信長が、以前に比べて自分たちを軽んじているのではないか、と悩んでいた。
このままではただの家臣に成り下がってしまうと考えた長政は、信長の盟友である純正に目をつけ、友好を結んで信長との軋轢をなくそうと考えていたのだ。
「材料や人夫を出すのは確かに負担だが、それで義兄上の覚えがめでたくなり、小佐々との友好も結べる。さらに街道を使った交易も盛んになるとなれば、やらぬ手はない」
純正は長政に、街道整備の一翼を担うことで有用性をアピールできると話したのだ。
「して、若狭はどうなのだ」
長政の顔が険しくなり、継潤の話を聞く。
「は、昨年の朝倉義景の侵攻後、表向きは国人衆は従っておりますが、逸見昌経(昌清)は高浜城に、粟屋勝久は国吉城(佐柿)に、熊谷直澄は大倉見城(井崎城)に割拠して半独立している様にございます」
ふむ、と長政はうなずき、考えている。
「その中で、ほどよく忠誠心があり、こちらの申し出に乗りそうな者はおるか」
継潤は少し考えていたが、
「されば、粟屋越中守勝久が適任かと」
「調略あたうか」
「おそらくは。勝久は現当主、といっても一乗谷に幽閉されておりますが、その現当主である元明は勝久が擁立したのです」
うむ、とうなずく長政。磯野員昌はじっと二人のやり取りを聞いている。
「先代の義統が、西若狭の逸見昌経が起こした謀反に対抗すべく、朝倉の軍勢を入れようとしましたので、反対して擁立したのです」
「それで?」
「はい、その後も朝倉とは敵対しており、朝倉のもとにいる元明からの降伏勧告にも従っておりません。国吉城にこもって抵抗を続けております」。
「ふむ、若狭武田を掲げてはいるが、傀儡となった元明の言うことはきかぬ、か。なるほど、反朝倉の国衆は他にもおろう?」
「は、武田家中が親朝倉と反朝倉に二分されてございます」
「その反朝倉の筆頭が粟屋勝久であるな」
「その通りにございます」
長政は考えている。やがて継潤と員昌に告げた。
「よし、継潤は若狭の反朝倉と加賀の一向宗へ本格的に調略をしかけよ。幕府軍として親朝倉の武藤を攻める、と。員昌は家臣団の意思を一つにするよう心掛けるのだ」。
ああそれから、と長政は続けた。
「公方様に若狭守護代の件、お話するのを忘れるなよ。ただ、あからさまにわれらが望んだ事を面には出さぬよういたせ。あくまでも公方様の希望で、となるようにするのだ」
「殿、大殿はどういたしますか」
「父は……そうであるな。いろいろとご苦労もされてきた。ここいらでゆっくり休んで貰っても良いであろう」。
すでに隠居していたが、完全に隠居して口出し無用に願おうということだ。
小浜をはじめとして丹生浦や常神浦の権益が欲しい。
若狭の次は丹後だ。その次は越前。さすれば義兄上も、この私を無視はできくなるであろう。今を逃せば、もう機は訪れぬ。織田は破竹の勢いで大きくなる。
そう考え、考えに考えた上に決心したのだ。朝倉を切り、織田とともに大きくなる。
■越前 一乗谷城
「との」
「との!」
「なんじゃ、騒々しい」
「上洛の件、どうされるのですか」
例によって家老の河合吉統と山崎吉家である。
二人は朝倉家の将来を考え、織田と敵対するのは得策ではないと判断し、小佐々と誼を通じるべく、京都の小佐々大使館に赴いていたのだ。
しかし当主である朝倉義景が乗り気でなく、信長同様に純正の事も田舎武者と見下していたので、純正の回答も良いはずがかなった。
このまま上洛を拒めば朝敵にされるかもしれない。そうでなくとも御内書にて討伐命令を受ければややこしい事になる。
幕府とは父孝景の功績によって親密であり、信頼もあったが、ここまで上洛命令を断れば、心証が悪くなるのは目に見えている。
上洛命令を出しているのが信長ではなく義昭である、と義景が思えれば良いのだ。
しかし、義景にとっては自分が為しえなかった将軍奉戴での上洛を、格下と思っていた信長が成し遂げたのだ。やっかみが入っていないと言えば嘘になるであろう。
「そのよう事、加賀の一向宗が危険だとか、いろいろと理由をつければよかろうが」
「理由はいかようにもつけられまする。しかし、力にてこられては、厳しゅうございます」
「力にて?」
義景が鼻で笑うようにして言った。
「いったい誰が、誰がこの越前に、義景に弓を向けるというのだ」
「殿、冷静にお考えください。今幕府では、若狭の守護を復権させようとの動きがございます。若狭武田の家中でも、朝倉派と公方様派にわかれて争っていると聞き及びます」
ふん、と義景は舌打ちのようにもとれる相槌をした。
「このような時に、名分を与えるような行動は慎むべきかと存じます」
「お主ら……さきほどから聞いておれば、信長をいたずらに恐れるような事ばかり言うではないか。なにを恐れる事がある。反信長はわしだけではないぞ、三好もおるし六角もおる」
そういって義景は反信長とおぼしき面々を挙げていく。
「それではあくまでもこのまま、上洛はせずじっとしておられる、と言うのですか」
「その通りだ、何度も言わせるな」
二人は、はは、と言って退座した。やはり、義景の状況認識は、甘かったのであろうか。義景の知らぬ間に、畿内周辺の情勢は大きく変わろうとしていたのだ。

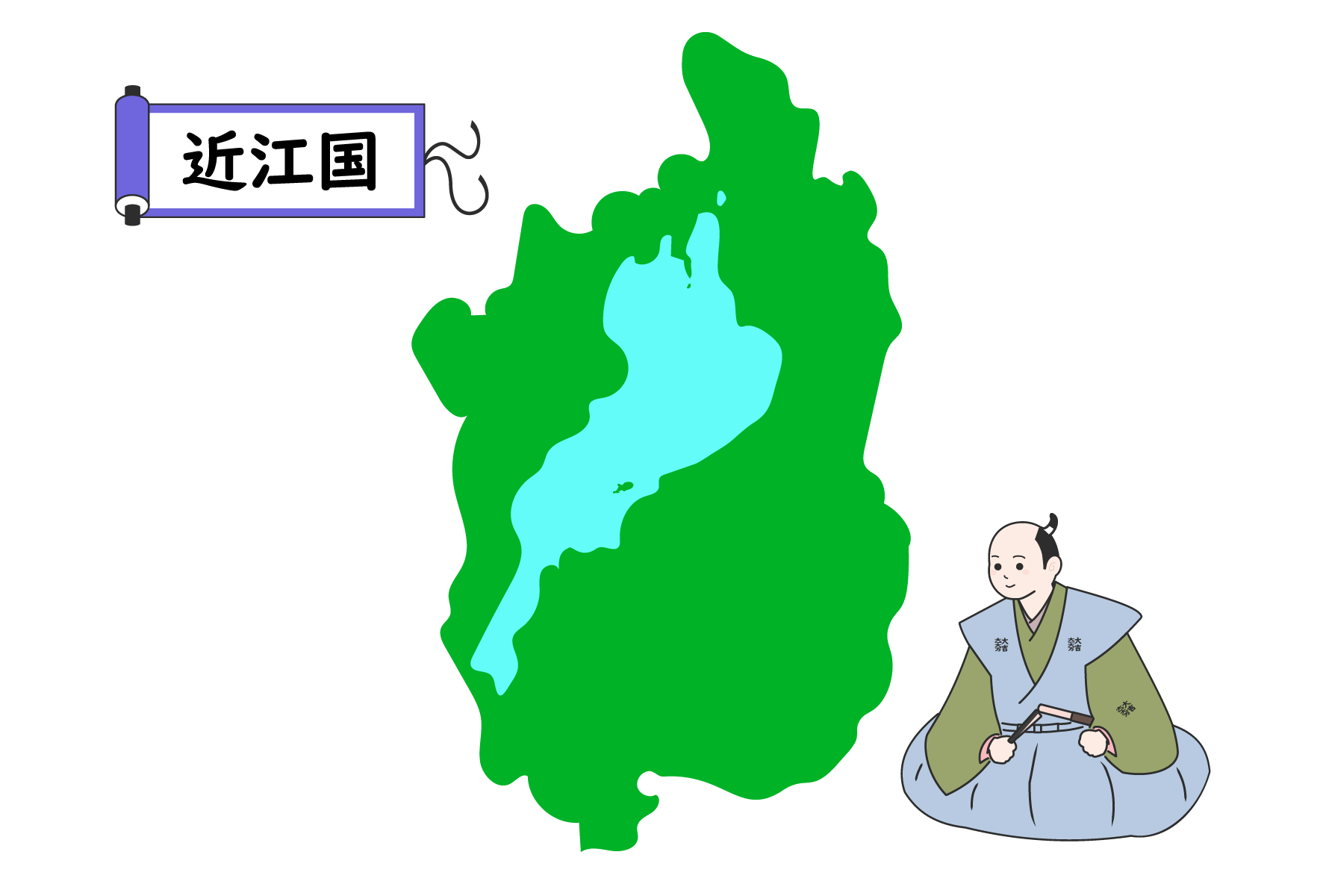


コメント