天正元年 三月二十一日 滋賀国
三好一族は没落の一途をたどっていた。
かつての天下人であった三好長慶がなくなり、上洛した信長によって都を追われ、再起を図った『和泉家原城の乱』(史実で言う本國寺の変・第279話参照)でも純正に惨敗を喫した。
その後野田城・福島城の戦いでは、世に言う信長包囲網の一角として戦いながらも、史実ほど勢力を回復できず、四国讃岐・阿波の一大名となっていたのだ。
一族の中でも誰が名跡を継ぐかで争い、河内半国の三好義継・摂津淡路の三好長治・讃岐阿波の三好存保(十河存保)に分かれ、そのうち河内の三好義継は信長に滅ぼされた。
「おい、見ろよ。三好だぞ」
摂津から河内を通り山城に入ったあたりからである。
『三階菱に釘抜』(さんがいびしにくぎぬき)の家紋を記した旗指物を掲げた、自分たちを見る周りの目が違うことに三好兵は気づいた。
何か、腫れ物にさわるような雰囲気なのである。
京都には純正の名代として大使の小佐々純久があり、畿内は信長が制している。都落ちした三好が入ってきても違和感しか感じないのだろう。
領民はみな、何しにきたんだ? と思っている。
「今さら来たところで、何にも出来ないだろうに……」
「大使様と織田の殿様にこてんぱんにやられるさ」
「また|軍《いくさ》が始まるのか?」
事情をよく知らない領民達は、口々に噂話をしている。
三好長慶以下、三人衆が悪政を敷いていた訳ではない。
ただ、その後に入った信長と小佐々純久があまりに優秀で、京の都の治安が完全に戻り、活気に|溢《あふ》れ人口も増えているのだ。
「あれ、なんだ? 小佐々の大使様と同じ旗もあるぞ。どうしたことだ」
行列を眺めていた町民は隣にいた友人に聞く。
小佐々家の家紋、七つ割平四つ目の旗指物である。三好の旗指物よりも長い竿で、高い場所に掲げられている。
「一時は日ノ本の副王だの、副将軍だの言われておったが、亡くなってからの三好は下り道であったからのう」
事情通のような男が語る。
「織田の殿様が美濃から上洛なさった時に、|軍《いくさ》に負けて阿波に逃れて、それからまた都に討ち入ろうとしたが、今度は小佐々の大使様に負けた。内輪もめもあった様で、今は小佐々家の郎等(家来)になっておるのよ」
「なんだ、そういう事なのか」
摂津三好軍は、二十一日には琵琶湖北岸へ到着し、陸路で敦賀を目指す事となった。
■京都
「麻呂は、麻呂は帰ってきた」
春の風 乗りて思ふは 京の夢 はるか遠くに 土佐を思へば
この和歌がこの世界の21世紀に残っているかはわからない。
そう感慨深く詩を読み、つぶやくのは、四国一条家当主の一条兼定である。
大友宗麟の娘婿であり、長宗我部元親に攻め滅ぼされそうなところを、純正の介入によって難を逃れた。
兼定は十九年前の天文十二年(1543)に一条房基の嫡男として、土佐国幡多郡中村で生まれている。
父の自殺後七歳で家督を継ぎ、大叔父である関白・一条房通の猶子と成って上洛していたのだ。
元服後に再び土佐へ下向するが、家の没落とともに、義兄である一条兼冬が当主を務める本家の一条家とも疎遠となっていた。
この土佐軍は、ある意味独特である。
連携という意味では一族のみの摂津三好軍に軍配があがり、個々の戦闘能力では九州勢が圧倒していた。
一条家は土佐七雄を束ねる家柄であるが、長宗我部家に滅亡寸前まで追いやられた経緯があり、安芸家は長宗我部家に滅ぼされ、純正の介入で家を復興していた。
純正の統制のもとひとつの軍となっているが、その実、連携がとれているとは思えない。
つい数年前までいがみ合い争っていた間柄である。立場上は兼定が束ねているが、将としての能力は、正直なところ長宗我部元親の方が上である。
「殿、この土佐の軍兵を、あの一条殿が率いるとは、得心できませぬ」
そう言って元親に詰め寄るのは、家老で家中随一の武闘派である福留隼人佐親政である。
「まあ、そう言うでない。弘恒はわずか齢十六、兼定は三十になるかと言うのに、まだ公家気質が抜けておらぬ。こたびの|軍《いくさ》は何が起こるかわからぬゆえ、楽しみだ。ふふふふふ……」
史実では四国を席巻した長宗我部家も、滅ぼした安芸家が復興し、一条家も目の上のたんこぶであり続けている。
力の差が歴然としていたので純正に屈服し、その政治手腕や国力の差に感服していたが、元親はまた、戦国大名であったのだ。
その野心は隠されているに過ぎなかった。
「殿、京の都にございますな」
家老の黒岩|掃部《かもん》が弘恒(安芸弘恒)に話しかける。
「うむ、まさかこの俺が京に来るとは思ってもおらなんだが……」
「は、誠に。然れどこたびは、四国土佐の軍兵として兵を率いてきておりますれば、恥じぬ戦いをせねばなりませぬ」
「心得ておる。然りながら元親が味方とは、未だ信じられぬ」
「左様にございます。親の敵と思い捲土重来を期しておった所を、御屋形様に成していただきました。そのご恩に十二分に報いる働きをいたしましょう」
安芸郡一万石を本領安堵してもらって家の再興を成した弘恒であったが、今以上に家を栄えさせようという願いはあったのだ。
「よう来られた。土佐守(一条兼定)に宮内少輔(長宗我部元親)、飛騨守(安芸弘恒)よ。さあ、ゆっくりされよ。道中問題はなかったか?」
「は、おかげ様をもちまして、三軍ともに無事入洛いたしましてございます」
純正の声がけに兼定が答える。
「そうか、先に入った三好は今ごろ琵琶湖を渡るところであろうが、なに、焦ることはない。皆が能登についてからが|軍《いくさ》だからな」
とかく先陣争いや、功をあせりがちな武将のあるあるを先にたしなめた。
「土佐守よ、義兄上には会われたのか? おれも朝廷ではよくしてもらっておる」
「宮内少輔よ、城下町はつつがなく払いしつらえて(整備)おるか?」
「飛騨守よ、義弟は息災か?」
各人にねぎらいの言葉をかけながら、純正は最後にしめくくった。
「良いか。決して功を焦って突き進むでないぞ。各々の禍根はあれど、今は味方であり、以後も味方である。自らの行いが味方を窮地に追い込む事にならぬよう、気をつけるのだぞ」
「「「はは、有り難きお言葉、心得ておりまする」」」
翌朝、休息を終えた土佐軍は琵琶湖へ向けて出発した。

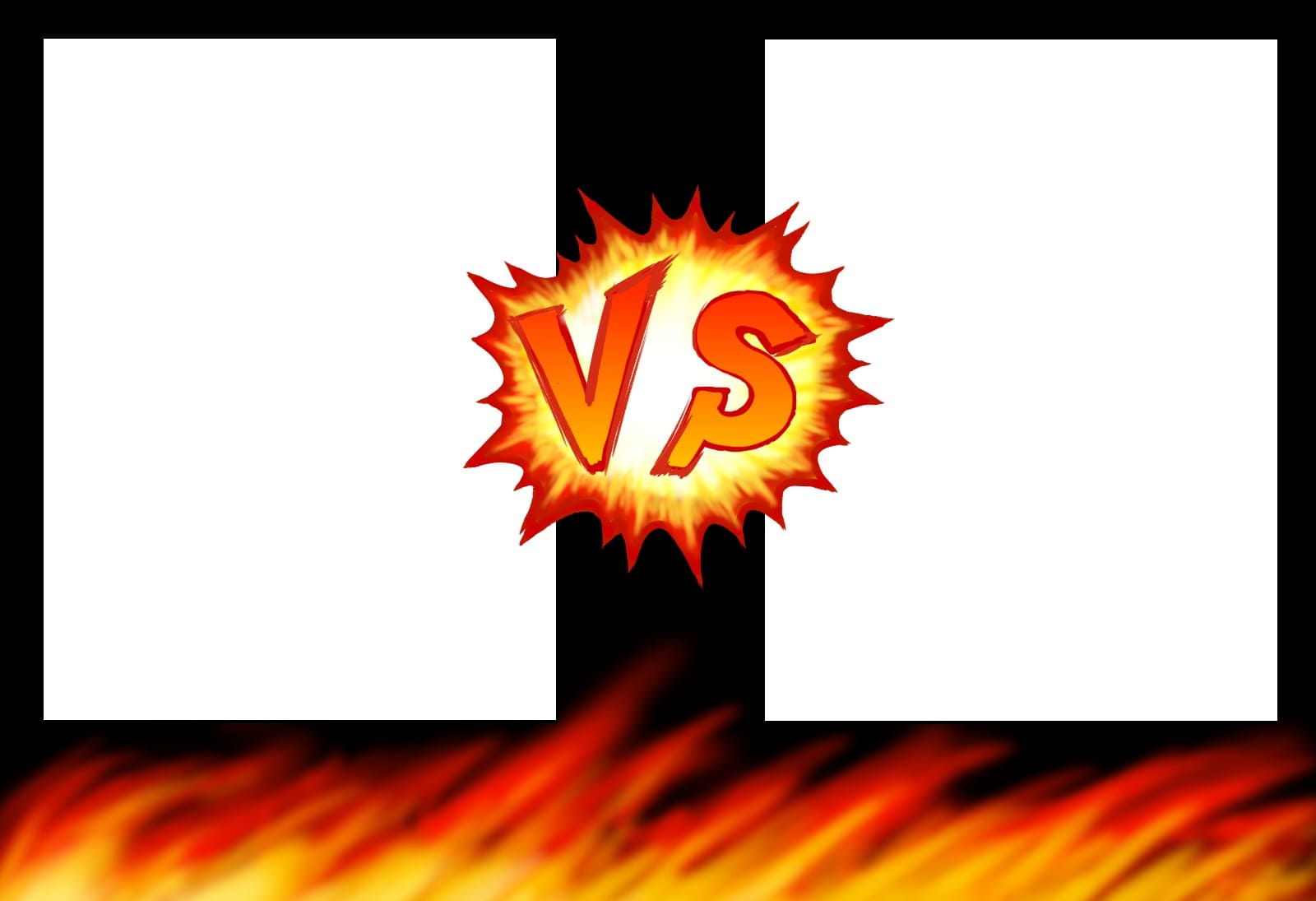


コメント