 対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む 第530話 はたして上杉謙信に小佐々純正は勝てるのだろうか?
天正元年(元亀三年・1572) 三月二十七日 京都 大使館 小佐々純正 さて、今の状況を整理してみよう。どうだろうか? まず、初動が遅れた事は否めない。今まで俺は軍事行動では先手先手を打ってきた。 しかし今回に限っては、状況判断が甘く遅かっ...
 対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む  対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む  対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む  対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む  対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む
対上杉謙信 奥州東国をも巻き込む  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ 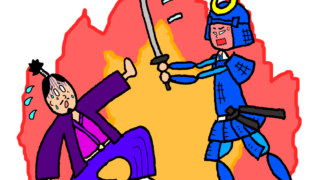 緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ 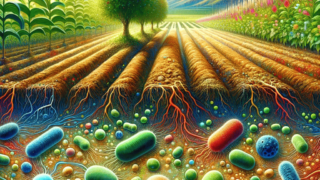 緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  緊迫の極東と、より東へ
緊迫の極東と、より東へ  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰 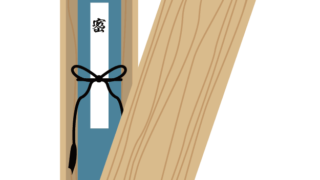 第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰 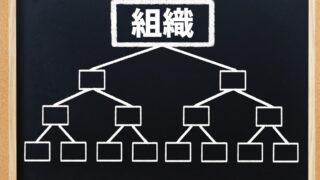 第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰
第2.5次信長包囲網と迫り来る陰 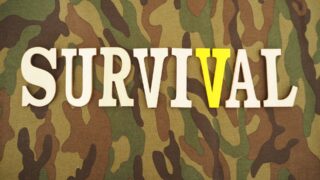 新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け
新たなる戦乱の幕開け  西国の動乱、まだ止まぬ
西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ
西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ
西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ
西国の動乱、まだ止まぬ 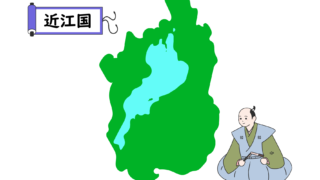 西国の動乱、まだ止まぬ
西国の動乱、まだ止まぬ