永禄十二年十一月二十日 諫早城 会議室
小佐々純正は政務の合間を縫って、子どもたちと遊んでいた。
子供だと思っていた弟の千寿丸は元服し、結婚して海軍兵学校へ入学している。甥っ子の幸若丸でさえ十一である。そろそろ元服を考えなくてはいけない。
それにしても、義姉は結婚しないのだろうかと純正は時折考える。純正本人は太田和家の家督を継いだ後、小佐々家を継いだ。
そして太田和家は弟の千寿丸が継いでいる。だから幸若丸としてはどこの家督も継ぐことは、現時点ではない。
誰か息子のいない男性と結婚してもらって、家を継がせるか? いやいや、そうなると生まれてきた子に家督を譲る、などと言いかねない。
ここは太田和家の分家をつくって……いや断絶している松島(瀬戸)小佐々の養子として入り、義姉を母としていくのがいいだろうか。
なにが一番いいのか、悩む。一度家族会議を開こうと考えた。
それから、中浦小佐々の甚五、もう六歳である。史実では今年生まれて、天正十年に使節団としてヨーロッパに行くのだが、現世の天正十年にはもう二十歳を越している。
歴史が変わってしまった。その他にもいろいろと変わって、もう異世界といった方が正しいかもしれない。同じ天正でも、キリスト一切関係ない使節にしようかな。
それから、自前の艦隊でポルトガルまでいく事を考えなければ。それにしてもフィリピンとの関係が決着して、ポルトガルと正式に同盟を結んでからだな。
若き当主小佐々純正のやるべき事は多い。
「殿」
「なんだ」
鍋島直茂と尾和谷弥三郎、それに佐志方庄兵衛の戦略会議室のメンバーである。
密室会談と思われたくないが、早い決断を必要とするときは骨子をこのメンバーで決め、合議に図るという流れになっていた。
「薩摩、大隅の国人衆からの返答書が届いております」
「うむ、どのような内容が多いか」
「は、弥三郎、読み上げよ」
直茂の指示で弥三郎が読み上げる。
「うーん、予想どおりと言えば予想通りだけど、やっぱり一と二が多いな」
「さようでございますね。やはりくれると言われても、素直には信じられないのでしょう」
送られてきた返書の半分が現状維持の国人待遇であった。残りの三分の二が本領安堵にて減った分を金銭にして俸禄支給である。
全額金銭支給希望もいたが、低石高の者がほとんどで、石高が低くなればなるほど多かった。
少ない石高ではやりくりも大変で、安定して俸禄をもらえるなら、それがいいという結論でなのだろう。
「いかがいたしましょうか」
「いかがも何も、そうだなあ……本当なら問答無用に全額銭で、と言いたいところだけど、厳しいな。国人の反乱は避けたいからね」。
純正は中央集権化を図るために、大友戦以降は問答無用で土地を召し上げ、俸禄制にして給料として金銭を支払う方式にしたかった。
しかし、現実はなかなか厳しく、反乱の事を考えると、意思を尊重せざるを得なかったのだ。
実際に国人をそのまま使うのは効率が悪い。
農繁期には動員が難しいし、税収もない。公共事業で街道を整備するにも制約があるので、諸々の事が面倒くさいのだ。
兵士にしても旧態依然としたものであるから、正規軍とは練度や装備の面で劣る。
可哀そうだが、尖兵としての捨て駒的な役割に限定されてしまう。これは純正の望むところではなかった。
人の生死を大事にしてきた純正であったが、戦死者が多くなると余計に国人の恨みを買いかねない。
「ん? これは、薩州島津や北郷、加治木や佐多に頴娃も、返答がないぞ、どういう事だ?」
純正は嫌な予感がした。薩州島津と言えば、伊東の重臣と会っていたと千方の報告で聞いていたからだ。なんだこれは? なにか関係があるのか?
「直茂、この薩摩と大隅、北郷は日向だが、先日決めた条件は間違いなく送っておるのだろうな?」
「は、もちろんにございます」
条件は以下のとおり。
薩州島津は二万五千石と年に一万二千貫、北郷は一万三千石と年に六千貫、加治木は九千石に六千貫、佐多は八千石に四千貫、頴娃は九千石に六千貫である。
「これは、この条件は安いか? 銭は不作の年でも変わらず与えるのだぞ。十分すぎる待遇ではないのか?」
「は、これ以上ない条件かと存じます」
直茂は率直な意見を述べる。
「ならばなぜだ? なぜ五人とも、全員、返事がないのだ?」
「……」
「直茂よ、おぬし、なにか俺に隠していないか?」
「は、滅相もございませぬ」
「本当か?」
「は、はい、本当です」
「なんだ、今間があったぞ。なんだ、なにか知っておるのか?」
純正の顔が少しずつ険しくなっていく。
「本当に知らないのだな? 後で露見すれば、いかにおぬしとて、ただではすまぬぞ」
しばらくの間、沈黙が流れた。庄兵衛と弥三郎は今にも窒息しそうだ。
「申し訳ございませぬ! この直茂、ひとえに殿のため、小佐々家中のためを思うてやった事にございます!」
直茂が後ずさり、平伏する。床である。
「なんだ、隠しておったのか。まさかと思うて言うてみたら、本当か?」
直茂は平伏したまま事のあらましを説明した。
「なにい!? 伊東と薩州にニセの使者を送り、さらに国人に噂をばら撒いたと?」
純正は驚き、そしてそれがどのような結果を招くか考えたのだ。
「まったく! なんで俺に言わずに黙ってやったのだ! バレたらどうするつもりだ? ニセの使者などバレれば間違いなく殺される。誰が、まさか石宗衆を使ったのか?」
直茂のはい、という返事に、憤りよりも、呆れと心配が先行した。しかし、危険性は高いものの、策の中身としては純正を納得させるものであった。
伊東はどう考えても先日の仕置きに納得していなかった。薩摩と大隅の国人が納得しているかなど、もっとわからない。
ここで不満分子を洗い出し、後の憂いを消しておこうというものだ。
「直茂、立ってくれ。お主の気持ちはようわかった。しかし、次からは必ず俺に教えろよ。いいか、次はないぞ」
石宗衆の千方景親は、父親に認めてもらいたかったのだろう。そんな事しなくても、千方は景親の事を十分認めている。会う度に報告とあわせて息子の話をしてくるのだ。
親の心子知らずの典型である。
純正の『次はないぞ』の冷めた蛇のような目に、凍りつくような戦慄を覚えた直茂であった。

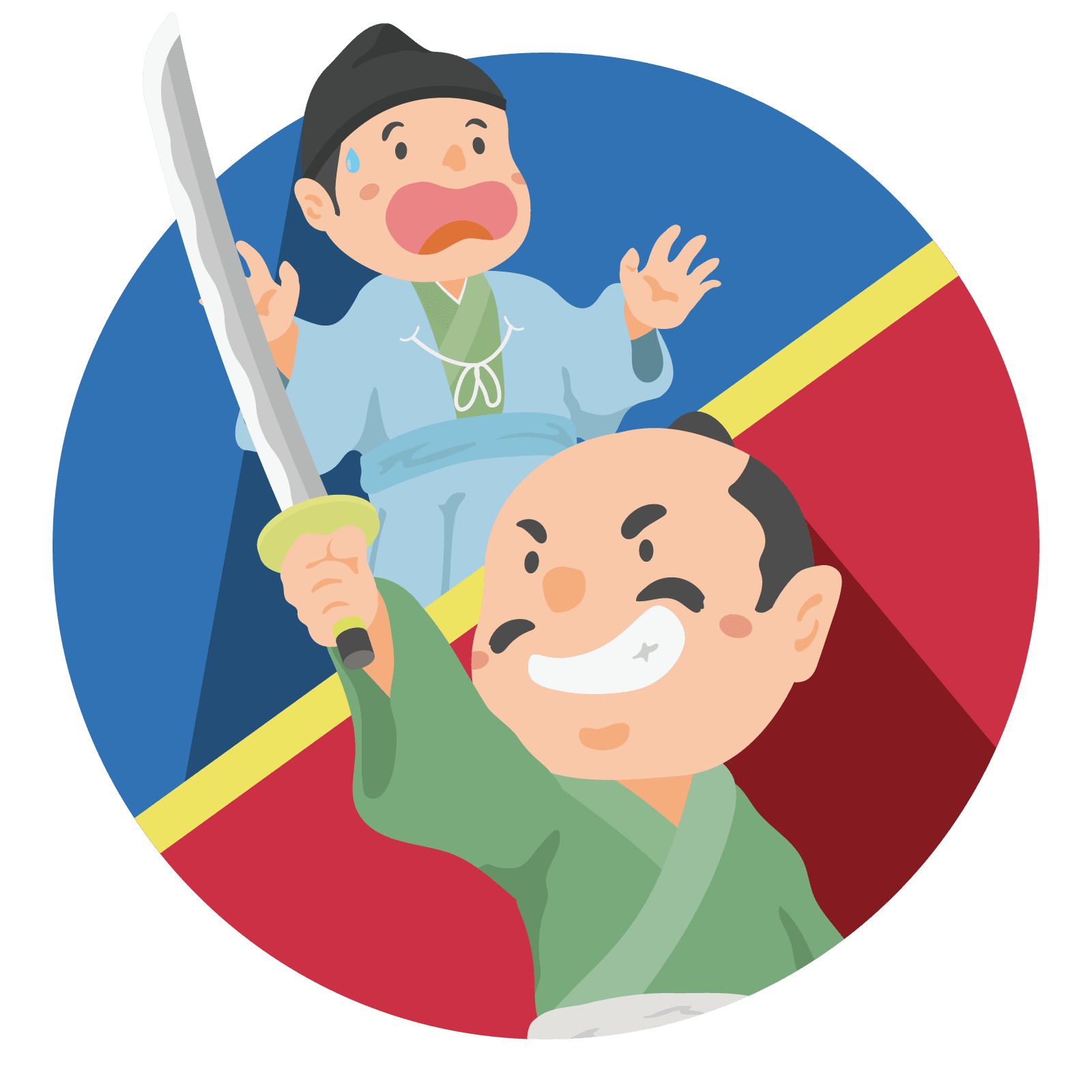


コメント