元亀元年 十月三日 岡山城
「殿、一つだけ、策がないこともございませぬ」
なに? と直家は秀安の言葉に目を輝かせる。さて、戸川秀安の腹案とはいったいなんであろうか?
「おお、なんじゃ」
「毛利にございます」
「何を言っておる。さきほど毛利はだめだと言ったではないか」。
「その先の話です。先の話を毛利とするのです」。
「一体どういうことじゃ?」
直家は真剣に秀安の話に聞き入る。
「まずは毛利に、尼子と小佐々のつながりを話すのです。昨年、一昨年とあれだけ手こずったのです。小佐々の支援があるとなれば、黙ってはおれぬでしょう」
「うむ」
「そして毛利の戦略は東進にござる。南も西も小佐々に押さえられている今、毛利は東に行くしか力を伸ばせませぬ。それゆえ伯耆因幡の国人を使って山名を圧迫し、われらに迫ってきているのです」
「それは明らかだな。そうすると宇都宮と西園寺の件も合点がいく。戦を長引かせて山陽、山陰へ介入させないようにしていたのだろう」
「はい、そこで毛利を焚きつけるのです。このままでは毛利は飲み込まれるぞ、と。小佐々は表向き戦を好まぬ主義で、危険が迫った時のみ反撃してきたそうですが、果たしてそうでしょうか」
「馬鹿なことを。それのみであそこまで大国になるものか。権謀術数の限りをつくし、他国を攻め取ってきたからに他ならぬ。戦とは大義と大義のぶつかり合いじゃ。すべて小佐々が正しいと、誰が言える」
「その通りです。それゆえ毛利も不可侵にとどめ、水面下で動き、勢力を拡げようとしているのです。ここで動かねば、次は毛利だと思わせるしかありませぬ」
「具体的にはどうするのじゃ」
「尼子の件、三村の件、そしてこたびの浦上の服属の件、全て話し、今立ち上がらねば毛利に未来はないと、煽りましょう。そして兵を起こすなら、今しかないと」
確かに、浦上が小佐々の庇護下に入り、因幡但馬の山名も小佐々派とすれば、毛利家としてはどこにも力を伸ばせない。ましてや尼子と結託されれば、いや、すでに結託しているのだが、毛利領内まで脅かされる事になる。
「それから伊予の件、おそらく毛利も薄々、露見していると感じているとは存じます。それを大義名分に小佐々は戦の機を見ているのです。尼子が蜂起し、浦上、山名、赤松、別所が小佐々についたとなれば、間違いなく戦をしかけましょう」
「そうなる前にわれらと組み、三村を犠牲にしてまでも、打って出るしか方法がないと思わせるのだな?」
「さようにございます」
直家は腕を組み、考える。確かに、それが今とれる唯一の手段か。
「……幕府を、公方様をなんとか利用できぬか。毛利に関してはそれしかないとしても、いま一つ決め手に欠けるゆえ、もう一手二手を打っておきたいのじゃ」
幕府の、将軍義昭の力をもって何かしようと言うのだろうか。
「さりとて……難しゅうござるな。味方につけるとなると、かなり骨が折れるかと」
秀安が言うことはもっともだ。
「なに、味方につけずとも良いのだ。敵の敵になりさえすれば良い」。
「と、言いますと?」
直家はニヤリと笑い、自分の考えを整理しつつ、秀安に話すことでまとめようとする。
「今の公方様は権威主義者で尊大で、自尊心が高いと聞いておる。それゆえ信長とは表面上は友好を保ちつつも、裏では各大名に御内書を送り自己の権力を強めようとしておる」
さきほどまで万事休すの手詰まり状態だったのが、少し光明が見えてきたようである。
「そしてそれは小佐々にも言えよう。御所への襲撃を防ぎ、多額の献金をしておる純正に対しても、先の三好との戦いで勝手に和議の条件を決め、あまつさえ服属までさせている事でへそを曲げているようだ」
「では、公方様に何をさせるのですか?」
「そうだな、例えば、だ。毛利と小佐々、山陽、山陰の大名国人に御内書を送らせるのよ。『播磨、美作、備前は毛利が統べるべし』とな」
「因幡但馬はどうなりますか」
「そこは放っておいても良い。いずれ毛利が食うであろう。要は小佐々と毛利を衝突させるのよ。毛利にとっては三村を敵に回すのは痛いが、長い目で見て播磨まで手に入れば、結果的に良しとなろう」
「なるほど」
「浦上や赤松、別所に他の国人どもも同じじゃ。あからさまに将軍の意には逆らえまい。それに織田にしても小佐々にしても、もうそろそろ、将軍に辟易しているのではないか?」
「そうですな。結局のところ、公方様の意図するところと、織田や小佐々が目指すことろの違いでしょうか」
「その通り、われらは権威を利用するが、それはつまるところ、自らの利のためじゃ。利がなくなれば、幕府などいらん。毛利は今のところ幕府にも織田にも誼を通じておる」
秀安は考えをまとめようとしている。
「つまり、幕府をつかって小佐々と毛利を敵対させれば、小佐々も表だって毛利に反抗できず、われらも毛利側に与して三村が討てる、という事ですな」
「その通りだ。秀安よ、その方毛利に行き輝元と両川を説得してまいれ。そして幕府には、誰が良いだろうか」
「殿、そのお役目、越後守殿しかなし得ますまい」
「あいわかった、幕府には花房越後守(正幸)を遣わすとしよう。越後守を呼べ」。
こうして宇喜多直家の生き残りをかけた大策略が動き出したのである。

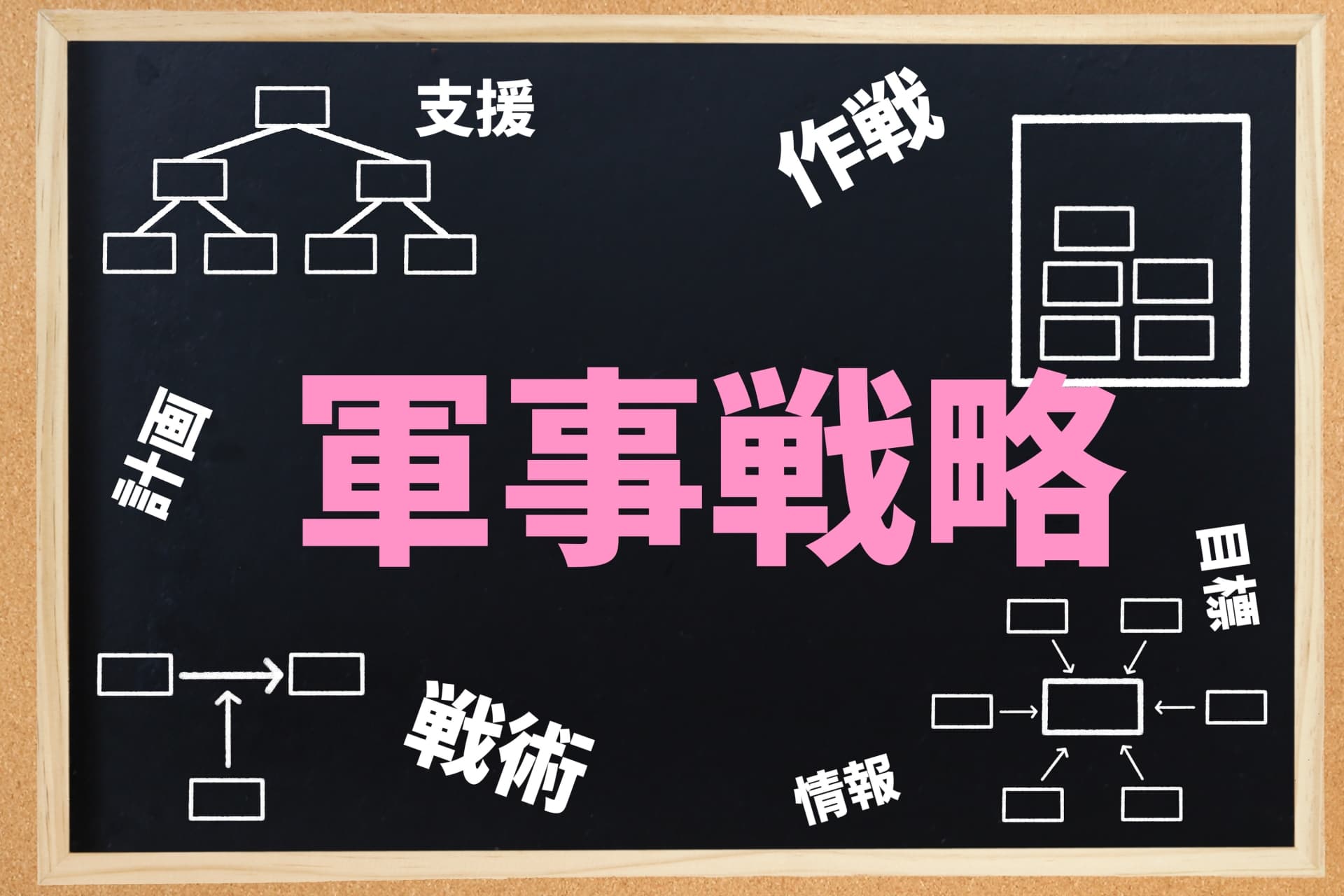


コメント