元亀二年 十月二十一日 信貴山城 織田軍本陣
勅書です! 信長さん
長い間戦乱が続いて、ようやく平和になってきたかな~と思ってたけど、またきな臭くなってきているような? という事をスゲー病んで考えて込んでる今日この頃。
理由のない戦争は無意味な流血にしかならんし、みんなが苦しむだけ。戦をせずに平和外交やってほしいと願ってるぞ。
あなたのすごさはみんなが知っている。
だからあなたには、もっと広い視野での状況分析や神様みたいな深ーい愛で、みんなを幸せにしてほしいと、真剣に願ってるんだ。
あなたのかしこい判断が、世界の未来を決めるだろうと信じている。不戦と平和な共存共栄の道を願っている。
超訳(?)すればこういう意味の勅書であった。
決して特定の誰かを、ましてや信長個人の行動を非難するものではない。あくまでぼやかしながら、戦争せずに平和に外交で収めてほしい、との内容である。
「さて、説明してもらおうか。いったいこれはどういう事か?」
信長のこの言葉には、なぜこの時期によくわからない勅書が届くのか? というものであった。
『誰々を討て』ではなく『和睦』でもなく、ただ単に戦争をせずに平和外交でやってくれ、など今さらだからだ。
「どういう事とは? 何を仰せなのか合点がいきませぬ。この勅書と同じものがわが殿にも届いておりまする。むろん、わが殿は戦を好まれませぬゆえ、同じ趣(意向)じゃと得心されておりました」
利三郎は平然と言い放つ。
実際にこの勅書は、利三郎ら三人が二条晴良を通じて朝廷に働きかけて出されたものである。信長に対して、暗にこれ以上戦をして勢力を拡げる事がないように、との意味があるのだ。
「……ふん。白々しいのお」
信長は小さく鼻で返事をすると、見定めるかのような眼差しで三人を見渡す。怒っている訳ではない。『ま~ったく!』というのが信長の心の声であろうか。
「ただの陣中見舞いに三人で来るわけなかろうが。中将殿の差し金か? いや、彼の御仁は回りくどいことは好まぬであろう。お主、利三郎と申したか? お主の考えか……おおよそ三人の誰かの入れ知恵であろうよ」
信長は順に軽く指を指しながら言う。三人とも何も言わない。
「一人は小佐々家の畿内から東の渉外すべてを取り仕切る治部少丞(純久)、そしてそれを統べる治部少輔(利三郎)、もう一人は中将殿の懐刀、鍋島左衛門大夫(直茂)……さて、ご用件を承ろうか」
一呼吸置いて、信長は本題を話すように利三郎に促す。
「は、されば申し上げまする。さきほど弾正忠様は、背いた者は討つと仰せでしたが、つぶさに教えていただく事は能いますか」
「つぶさにだと?」
少し驚いたような信長であったが、すぐに喋りだした。
「事ここにいたっては、公方様がわしを討てと理不尽な御内書を方々に送ってしもうたゆえ、まるでわしが逆賊のように思われておるが、そうではない。それは得心しておるであろうの?」
信長は合点でも承知でもなく、あえて得心という言葉を使った。
織田と小佐々は、純正が九州を出る前からのつきあいであるし、これまでの経緯は、信長と純正が定めた(話し合いで合意した暗黙の了解)ものには違反していないと言いたいのだ。
「然る事(もちろん)にござる」
「然れば、そうよの……。松永、本願寺、雑賀はもちろん、朝倉に……。わはははは。浅井と徳川を除く、この畿内とその周りぜんぶじゃわい!」
信長は大声で笑って見せたが、もちろん面白いから笑ったわけではない。この場の間を持たせようとして、単なる場つなぎ的に笑っただけなのだ。
「……されば、武田はいかが相成りましょうや?」
「無論、叩く。が、今ではない。信玄が果てたゆえ彼奴らもすぐには動けまい。一年、いや二、三年は勝頼のもと領内をとりまとめるであろう」
小佐々にとっては、武田以外は正直どうでもいい。
信長が畿内とその周囲を統治するのは織り込み済みで、その先の話をしたかったのだ。そのためにあえて、利三郎は本願寺や松永などの話をした。
「左様にございますか。では、本願寺や松永などが和睦を申し出てきたならば、いかがいたしますか?」
「和睦など笑止千万、降伏ならば受け入れよう。われらに和睦せねばならぬ理由はない。信玄が生きているのならば、まだ和睦もあったであろうがな」
「生きてますぞ」
……。
「何と?」
「徳栄軒信玄殿は、生きておられます」
「は! 何も申すかと思えば馬鹿な事を! 信玄は死んでおろう! 三河の野田城から退いたとき、何やら怪しき動きと思いて透波を放っておったら、諏訪神社の神人が方々に起請文を書いて遣わすを認めておる!」
信長は思わず大声を出してしまった。
「然もありなんと存じます。神社の神人や御宿友綱、松坂法印などの侍医は固く口を閉ざしても、助手や小間使いの中には信玄公が身罷られたと、嘘の伝聞を流す者もいたでしょう」
「嘘だと? !」
諏訪神社や侍医の周りでの透波による情報収集にて、信玄が死んだ事が確実視されていたのだ。もし、信玄が生きているのなら、信長の基本戦略が根底から覆される。
三年どころではない。病気が癒えればすぐにでも再度侵攻してくるだろう。
しかしなぜだ? なぜ得にもならない嘘をばら撒いたのだ? 信長の疑問は絶えない。
「異な事を申すでない。なぜ嘘など流さねばならぬのだ。生きておるのならば、退く要なしではないか」
「生きておっても養生せねば命が危うい、としてもでござるか? 生きておれば、再起もできましょう。然りながら、十分に療養もできずに戦場におりては、再起も望めませぬ」
信長は少しずつ声が落ち着いてきたが、利三郎は冷静に、淡々と話を続ける。
「では死んだとの報せはどうなのだ? われらは確かなる証をもって信玄が死んだと言うておるのだぞ?」
「それが深謀遠慮なのでしょう。まさに鬼神の如き。古の孫子に勝るとも劣りませぬ。死せる孔明生ける仲達を走らす、ではございませぬが、こたびはその逆さま(反対)にございましょう」
「どういう事じゃ?」
「三河より退きし事、これは致し方のなきこと。それによりて起きる事はどうにも出来ませぬ。然りながら、信玄公が死して諸侯がどう動くか、誰が敵で誰が味方かを知る事はできまする」
利三郎の話を聞きながら、信長は目をつむり、じっと考えている。
「家中はもとより、武田に与している国人衆の動きも調べる事あたうのでございます。それによりて何を重んじ、誰を信ずべきか。四郎殿の代においてどのようにすべきかを見ているのです」
……。
しばらくの沈黙が流れ、誰が先に発言するか、様子をお互いに見ている。
「……。ふむ。しかし、お主よう知っておるのう。まるで武田と誼を通じ、内情を教えて貰ったかのようではないか」
「! 滅相もございませぬ。わが小佐々家は織田弾正忠様と懇意にしており、よしんば武田と結ぶとしても、それは弾正忠様と武田との間で和議がなり、互いに親交あっての事にございます」
「まあよい。疑っている訳ではない。然れどお主らは、われら織田が東へ東へと力を延ばし、領国を拡げて大きゅうなるのを恐れているのではないか? それならばわしも、言わせて貰おう」
「なんでございましょう」
「わしが何も知らぬと思うておるかも知れぬが、勘九郎(信忠)や七兵衛(津田信澄)から毎月のように文が届いておるからの。南蛮との交易に飽き足らず、直に呂宋(フィリピン)や高山国(台湾)へ船を出して、足溜(拠点)を作っておるだろう?」
おそらくこれは予想できた事だ。
軍事情報のある程度の共有は純正と信長の間で合意があった事だが、これは違う。公然と行っている事なので、信長の耳に入らない方がおかしい。
「さらに南蛮には他にも富春やアユタヤ、マラッカやバンテンなどの多くの国があると聞く。それらと直に交易し、南蛮でとれる産物も高山国で栽培し、琉球でもつくっておるというではないか」
三人とも黙って信長の話を聞いている。直茂と純久は立場上口を挟めない。
「仰せの通りにございます」
「自前の船でそこまでやるとは、にわかには信じられぬが、誠であろう。そこまで銭を儲けてどうするのだ? もう十分に小佐々の領国は富み栄えているではないか。これよりさらに、何を望むのだ」
しばらくの沈黙の後、利三郎が口を開いた。
「それは、御屋形様が穏やかにて安らかなる、誰にも邪魔されぬ領国を作りたいと願われているからにございます。その行いの果てに日ノ本の西半分を統べるようになりましたが、正直なところ……」
「なんじゃ?」
「まだ、足りぬのです。銭がふつに(まったく)足りぬのです。年貢も運上金も増えましたが、入目(支出)も増えているのでございます。領国が増えたのはその志にあらず、果ての事なのです」
「なぜじゃ? 中将殿とわしは西と東、いや、確かなる証を立てている訳ではないが、わしは中将殿と争う気など毛ほども持たぬ。それなのになぜ、銭がかように要るのだ?」
「仰せの通りにございます。然りながら御屋形様はなにやら、先の先まで考えているようにございます。領国を富ませ、今までの日ノ本では考えられぬ事を、次々に考えておいでにございます」
「ふむ……。まあ、良い。戦道具をそろえ、軍兵を備えるは攻める為にあらず、守りの為、という事だな?」
「左様にございます」
「あいわかった。いたづらに戦はせぬ。守りのための戦に徹すといたそう。武田は……そうであるな。信玄が存命かは別として、条件次第では和議をしても良い。のめるかどうかは、わからぬがな」
「……は。では、織田に仇なす者でなければ我らが交易をしても、事ともぜず(問題にしない)と受けとってもよろしいのでしょうか」
「……良い。……ああそれから、お主ら、蝦夷地に向こうてはおらぬか? 西半分を取られておるのに、蝦夷地や奥州まで取られては……まあわしの物ではないから何とも言えぬがな」
「それは一体どういう事にござるか?」
「いやなに、異な噂を聞いたのでな。若狭の商人が越後から船で来るときに、小佐々の家紋が入った珍しい船を見かけた、しかも岸側ではなくて沖側だと」
「……見間違いでございましょう」
利三郎は全否定した。
こうして、織田と武田の和睦の可能性が、ゼロではない事がわかった。

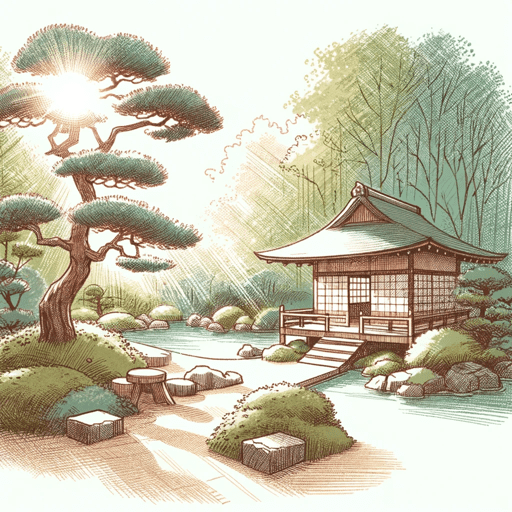


コメント